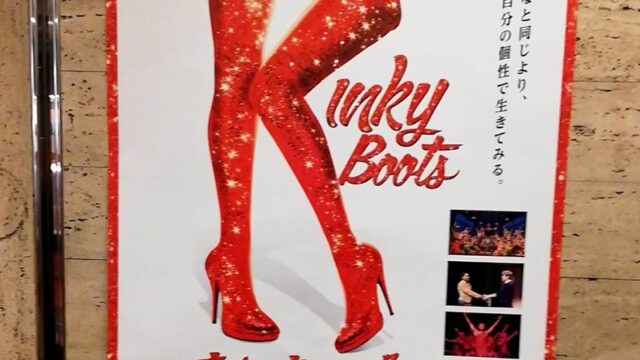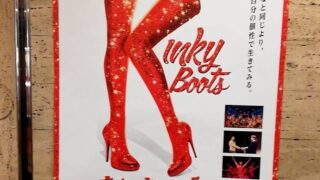もともとは、ミュージシャンの斎藤和義さんが、ベストセラー作家の伊坂幸太郎さんに『恋愛をテーマにしたアルバムを作るので、「出会い」にあたる曲の歌詞を書いてくれないか』と頼んだことがはじまり。伊坂さんが「作詞はできないけど小説を書くことなら」と言って、「アイネクライネ」という短編小説を書いくれた、という経緯があったんですね。この話だけでも既に、なんつー贅沢な話!と思います…
この短編小説を曲にしたのが、斎藤さんの「ベリーベリーストロング~アイネクライネ~」。この歌詞は、短編小説「アイネクライネ」をめちゃめちゃセンス良く要約したもので、ほとんど映画のあらすじと言ってもいいくらいです。
映画でも「ベリーベリーストロング」というセリフが登場し、佐藤(三浦春馬)が「なんで英語なんだよっ」と突っ込んでいますが、そりゃあなた、斎藤さんの曲に使うなら「すごくすごく強い」って言うより「ベリーベリーストロング」の方がいいに決まっているからです…

その後、書き足された短編小説を一冊にまとめて、小説「アイネクライネナハトムジーク」が誕生!これがベストセラーとなり(現在では56万部)、映画が作られ、その主題歌として「小さな夜」が生まれ、コミカライズもされたわけですが、それらの制作には、ほぼほぼ伊坂さんの好きな作り手がオファーされています。ベストセラー作家をつかまえて言うのも恐縮ですが、いや~気が合うな。好きな人、全員同じ!!
まず映画は今泉力哉監督。「愛がなんだ」で有名になりましたが、伊坂さんは「こっぴどい猫」を観て好きになったとのこと。主題歌は言うまでもなく斎藤和義さん。そもそも伊坂さんは斎藤さんの大ファンを公言しており、苦手な(本人説)恋愛小説を頑張って書いたのも、斎藤さんが好きだからこそ。主演の三浦春馬さんは、16歳の頃に伊坂さんの「チルドレン」に出演したご縁ですね!
そしてコミカライズは、なんと!いくえみ綾先生に頼んだって言うじゃありませんか。これは外せないです。三浦春馬さんのいくえみ男子っぷりはどうだったのか?確かめないといけないので。
※以下、映画の内容に少し触れていきます。未鑑賞の方はご了承いただける方のみ、または鑑賞後にご覧いただけると幸いです。

三浦春馬さんと言えば①「走る」②「ふり向く」③「びしょ濡れになる」のどれかが入るとカッコ良さ3割増しになると思うのですが、映画「アイネクライネナハトムジーク」の冒頭では、②の「ふり向く」が最も重要な場面で使われます。仙台駅前のペデストリアンデッキの上で、佐藤が小さな音楽に気が付いて、ふり向いた瞬間です。
この瞬間が、「出会いというもの」の瞬間を表現しているのだと気が付いたのは、小説を読んだ後でした。
出会いとは、、、
「その時は何だか分からなくて、ただの風かなあ、と思ってたんだけど、後になって、分かるもの。ああ、思えば、あれがそもそもの出会いだったんだな、って。これが出会いだってその瞬間に感じるんじゃなくて、後でね、思い返して分かるもの」(小説より抜粋)
そして、その「出会い」が「小さく聞こえてくる、夜の音楽」みたいだと小説では言っています。(ドイツ語で「ある、小さな、夜の曲」は「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」。タイトルは、モーツアルトの曲名でもあったのですね)。
この「出会い」の話が、なるほど!と思わされるのは、映画の終盤近くになりますので、ここでは、冒頭の「ふり向く」シーンについてもう少し触れてみたいと思います。
ある夜、佐藤は寒空の下で街頭アンケートの仕事をしています。道行く人々に無視され、素通りされます。デッキの上からは大きな画面が見えますが、その日は日本人ボクサーのヘビー級タイトルマッチがあり、人々はそれを観ようと佐藤に背を向けて群がっています。佐藤はため息をこらえて、にぎやかな音を出す大画面を見上げます。
…と、その時、ストリートミュージシャンの歌声が小さく聞こえてくることに気が付いた佐藤は反対側をふり向きます。
…すると、この時!アップになっている佐藤の横顔が、ほくろのある側からほくろのない側に変わります。
三浦春馬さんと言えば、ほくろのある側が「効き顔」と思い込んでいました。いつも「わー、なんだなんだ、このイケメンは!」と思うような映像は、下顎に必ずほくろが見えていたからです。おそらくは、このほくろからフェロモンのような何かが出ているのだろうと思っていました。
しかし「アイネクライネナハトムジーク」で演じる「佐藤」は、下の名前もない、ただの「佐藤」。ごく普通の人ですよ、と名前からして強調していますから、あまりカッコ良くても困ります。個人的予想では、ほくろのない側から撮ったシーンを多く用いて、なるべく冴えない感じを出すのでは?と思っていました。
ところが!この冒頭の振り向くシーンでは、ほくろのある側だけでなく、ほくろのない側の横顔がとても綺麗でした。しかも、ほくろのない側の横顔は、タイトルバックの直前でもう一度アップで使われており、この時、「まばたき」から何か切ない感じのフェロモンが出ているような気がしたんです…いや、絶対まつ毛から何か出ている!(断言)
美しい横顔。ほくろのある側とない側の両方の横顔がアップが、映画の「つかみ」とも言える冒頭で出てくるとは!なんとも贅沢な貴重映像です。この映画は財産です。
この少し後に、佐藤は紗季ちゃん(多部未華子)と実際に出会うわけですが、本人はそれが運命的な「出会い」とはつゆ知らず、寒空の下、仕事の辛さや理不尽や落ち込みをこらえて、立ち尽くしています。すばらしい「出会い」の瞬間は、最悪と思っている時に来ないとも限らない、ってことですね…

この映画の大きな魅力のひとつは、気の利いたくり返しが効いていることです。素敵なくり返しに出会うたびに、小さな感動が少しずつ重なって、この映画が何を言っているのか、だんだん濃くなってきます。
カノンのような、美しいくり返しの表現は、「出会いのつながっていく不思議さ」「誰かと出会って、好きと嫌いをくり返し、命がつながっていく不思議さ」という映画全体から伝わってくるメッセージと、とてもよく合っていると思います。
一つの出会いが、思わぬ所で、思わぬ人とつながって、「うそぉ、ここでつながっているの!?」と何度も思わされます。
中でも涙腺崩壊したのは、(きっと同じ場面で泣いた人、いると思うのですが)ボクサー(ウインストン小野)の試合の場面です。
※以下、大きくネタバレします。ご注意ください。
ボロボロになったボクサーのウインストン小野に、もう一度立ち上がるモチベーションを与えたのは、10年前にたった一度、公園で出会った耳の悪い男の子でした。ほんの少しの時間、たった一度の心の交流が、10年たっても心に残っていて、それが爆発的な力を与えてくれたと思うと、誰かと「出会う」ことは、凄いことです。
このシーンでの感動も、くり返しの上手さが与えてくれたものです。10年前、公園で出会ったこと。少年のお姉さんから教えてもらった「大丈夫」という手話。ウインストン小野だけが折れた木の棒。その時交わした少しの会話。そして、ボクサーが立ち上がる直前のシーンでは、10年前の公園のシーンと同じ音楽が流れます。記憶力があやしい自分ですが、音楽と記憶は連結しているらしく、この音楽が流れた瞬間、公園でのシーンをまざまざと思い出すことができました。ここで涙腺崩壊。
この映画は、群像劇ですから、それぞれの登場人物が、それぞれの出会いの素晴らしさを伝えてくれるわけで、自分はここが一番感動した場面でした。恋愛とは全然関係ない所でしたね…
でも大丈夫。メインとなるラブストーリー部門は、佐藤と紗季ちゃんが責任もって伝えてくれました。ボクサーの場面の感動とは、また違う、胸にじんわりと温かいものが来る感じ。この感じが、気持ちのいい鑑賞後感の決め手になっているんだと思います。
ラストシーン直前の紗季ちゃんのセリフも、やっぱりくり返しが効いていますよね。出会った時の会話を覚えていて、10年経ってプロポーズされた時に使うとは!そして、ラストシーンで、ペデストリアンデッキの上(出会いの場所)に並ぶ2人が、佐藤と紗季ちゃんではなく、美緒と美緒のボーイフレンドになるかもしれない男のコだったこと。ここらへんが、美しい旋律をくり返すカノンに似ていると思いました。

ただね…この映画が最も明確に言っていること=「劇的な出会いよりもっと大切なことは、後になって、この人で本当に良かった、って思えること」っていう主訴。これは頭では理解できるけど、どこまで共感できるか?と言うと、結構むずかしい。
目の前にいる人を見て「ナイス判断だったな、オレ!」って思える人って、何パーセント位いるかな?
一回、佐藤の勤務先のマーケティング・リサーチの会社に頼んで、アンケートを取ってみた方が良くないですか?
特に、織田由美さんは、欲のない人だなと気になりました。だいたい紗季ちゃんも10年も同棲していて、文句言わない、出産年齢とか自己実現とか言い出さないのって、これって普通かな?
女性とは?いかなるものかと言うと、
相手が三浦春馬なら何も言わないが、佐藤だったら結構言う人が多数を占めるでしょう。
しかし、この映画から自分に伝わってきたことは、もっといい事でした。
劇的な出会いがなくても、相手がこの人で良かったと思えなかったとしても(程度問題ではありますが)別にいいと思えます。
ウィンストン小野がボクシングのグローブで「大丈夫」の手話をし、佐藤もまた転んでいる子供に「大丈夫」の手話をします。ややくどい目に感じた人もいるかもしれませんが、大切なことは、目の前の人が誰であれ「大丈夫?」と言えればいいんじゃないのかな?と思えました。佐藤のようにウィンストン小野のサインをもらってこれたら…何か自分にできることがあれば尚いいのでしょう。「大丈夫?」と聞いて、「大丈夫じゃない」と言われたことは、あまりありませんが。
終盤になって、佐藤がベージュの下町ロケット風のジャンパーを羽織って、走って走って走って、ゼイゼイ言っている頃になると、そんなことが伝わってきました。

佐藤というキャラクターを三浦春馬さんは、どのように演じたのでしょうか?
原作では、10年後の佐藤は登場しません。劇的な出会いを待つだけの男、27歳の佐藤(三浦春馬)が、同い年の紗季ちゃん(多部未華子)と出会い、胸にほわっと「いい予感」が来たところで終わります(まだ付き合っていません…)。
原作ではまだ付き合ってもいないんですから、10年後の佐藤は完全に映画のオリジナルです。小説で出会った2人が、その後どうなったか?「この人で良かった!」と思える「出会い」だったのかどうか?それを追跡するための妄想とも言えますが、「劇的な出会いより、もっと大切なことがある」という原作が示すテーマを描くためには、確かに必要です。
この10年後の佐藤が面白いんだと思います。(原作から考えると37歳になっています)
一言でいうと、27歳の時のキャラクターから言って、なんで10年間も結婚しなかったのかが、謎なんです。
27歳ではあんなに待っていた「劇的な出会い」をせっかく果たしたのに、37歳になってみたら、紗季ちゃんと10年間も同棲したまんま。
10年間の交際の様子は一切描かれず、「10年後」はいきなりプロポーズの場面からだったので、佐藤の立ち振る舞いから想像するしかありません。プロポーズのまぬけな結果やその後の生活の様子を見ても、なんで結婚しなかったのか?私にはなかなか見えてきませんでした。
ようやく見えてきたのは、アイスクリームを食べるシーンでしょうか。佐藤がわびしい生活をしている真っ只中、高校生の美緒からずばり「出会ったのが紗季ちゃんで良かった?」と聞かれていますが、きょとーん…としてるんですもん。
ここでも、まつ毛バサバサさせて瞬きして、何かしら内面に刺激とか動きがあったんだろうとは思えども、このあたりから「だめだ、こりゃ」という気分がこみ上げてきました。この期に及んで、まだきょとんとしているんじゃ、見込みはないな。と。
しかし、佐藤がバスを追いかけて走るシーンが始まると、身を乗り出して観ることになります。いやー、バスの中から佐藤の様子を伺っている紗季ちゃんの表情を見た時は、ああ、もう大丈夫、これで一安心、と思ったんですがね…
この後に起こったことは、一言でいうと、佐藤は優しいけど少しだけバカだったってことです。ラブストーリーの山場かな?っていう、一番いい所で紗季ちゃんをバスに乗せちゃうんですもん。ここで、10年間結婚しなかった理由はここにあるんだな、と思いました。その時の「キラースマイル」と言われる全開の笑顔を見て、やっと納得。スッキリしました。
バカと言っても、まあ悪いバカじゃないんだし、まあ少しくらいバカでも別に差し支えないよね、って思える。
佐藤って、優しいけど少しばか。ばかな所が、すごく愛おしい。

いくえみ綾先生によるコミカライズ版は、小説の内容をほぼ踏襲しているので、描かれているのは27歳の佐藤のみ。「いくえみ男子」と言われる、2次元と3次元を行ったり来たりするイケメンとしても魅力的な佐藤が、違和感なく描かれていました。
映画の27歳の佐藤も、あまりカッコ良くならないよう気を付けているとはいえ、社会人5年生の好青年。個人的には漫画の佐藤と比べて遜色なし!全然イケるよね。いい人そうだったし、友達の家でそうめん食べたりして、親しみの持てるイケメンという感じ。
ただ、漫画のすばらしい所は、「出会い」を「小さく聞こえてくる、夜の音楽みたい」という例えが大切に描かれていたことです。小説を読んでいて、ここは自分でイメージするのはなかなか難しかった。映画ではセリフで表現することは避け、映像で表現していていましたが、分かりやすさという点では、漫画が一番しっくり来ました。
漫画を読んでみると、自分が小説読んで膨らませたイメージより、ずうっと素敵な世界観がそこにあるんですよね…それは絵だけじゃなくて、ピックアップしているセリフや文章や、強弱のつけ方。いろいろと自分ではイメージできなかった部分も描かれていました。
街頭アンケートを取っている佐藤がすごく可愛いくて、ちょくちょく開いてみたい漫画になりました!

「出会いがないというすべての人へ」というキャッチフレーズを目にして、面白そうだなと思って観たのですが、その「出会い」の意味は、思っていたよりずっと広くて深かった。
「出会い」はその人の意志を作る成分になっているんじゃないか?ちょっと大げさかもしれないけど、そんなことを思いました。
目立ちたいとか、勝ちたいとか、褒められたいとか、あいつにだけは見下されたくないとか。そんな感情からはずっとずっと遠い所に連れて行ってくれる、気持ちのいい鑑賞後感。また観返したくなる作品です。
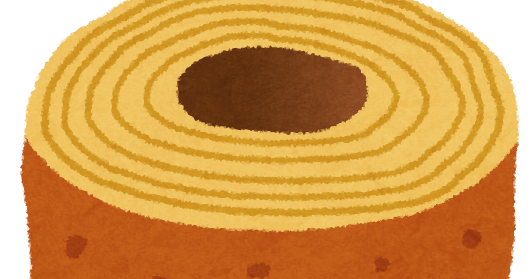

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/461fbebe.7a47c8db.461fbebf.891da477/?me_id=1379988&item_id=10002938&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff016918-betsukai%2Fcabinet%2F07065206%2Ffarmfoods%2Fimgrc0102840917.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)